エンジニアにとって、変化の激しいIT業界を生き抜くうえで欠かせないのが

イベントでは、岩本さんが試行錯誤を重ねて培った勉強のノウハウが語られました。本記事では、その内容をもとに
1. 合格ラインを超えるコツ
まずは、合格に必要な知識や得点力を、どう身につけていくかを解説します。
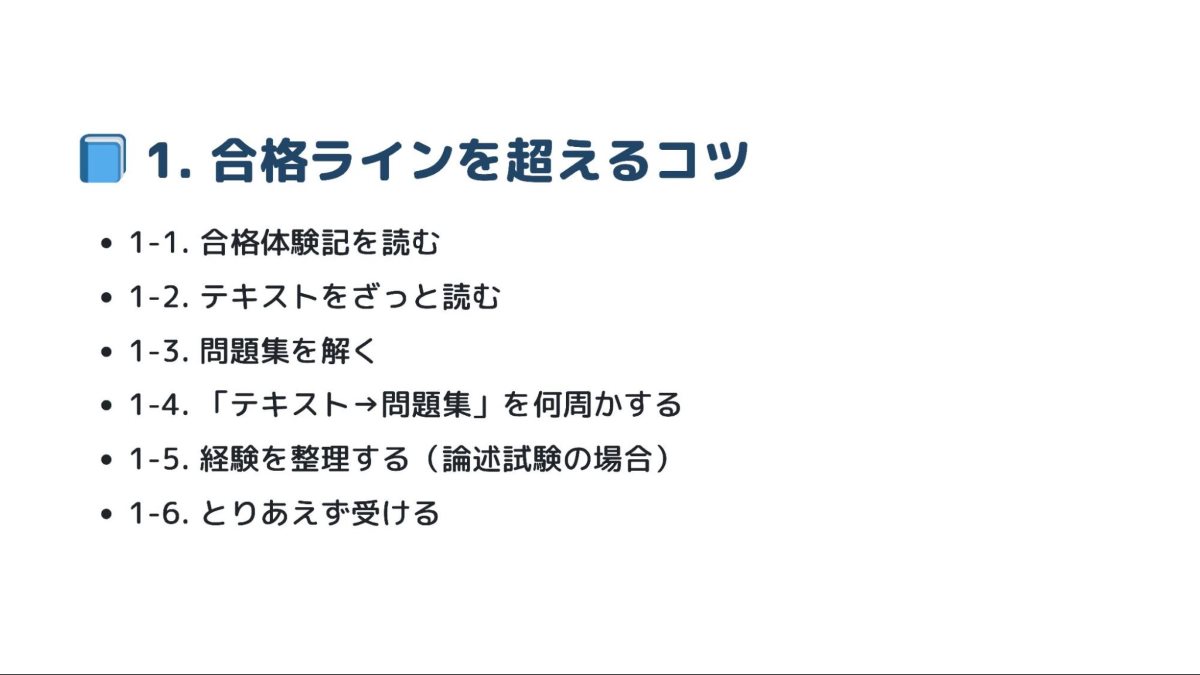
1-1. 合格体験記を読む
資格試験の勉強を始める際、合格体験記を読むことは非常に有効です。すでに合格した先人たちの
岩本さんの場合は、1カ月ほどが集中力の持続する限界と感じていることから、勉強期間は概ね1カ月を目安にしました。ただし、この期間は人によって合う・
おすすめの情報源として、
1-2. テキストをざっと読む
合格体験記を参考にして、おすすめされているテキストを入手しましょう。多くの場合、テキストは数百ページにおよぶため、最初から集中して読み切るのは大変です。岩本さんの場合、最初の一周は
その後、何周も読むことになるので、最初からすべてを覚えようとするのではなく、全体像をつかむくらいの軽い気持ちで読み進めるのがおすすめです。試験の内容を大まかに把握することで、その後の学習もスムーズになります。
1-3. 問題集を解く
岩本さんが最も重要だと考えているのが、過去問を繰り返し解くことです。予想問題を解くのも一つの方法ですが、実際の試験では過去問と似た問題が出題されるケースも多いため、まずは過去問を優先するのがおすすめです。
特に直近の3回分以上を解いておくと、出題傾向がつかめるだけでなく、本番に向けた安心感も得られます。また、解くだけで終わらせず、必ず採点して得点を記録することも大切です。たとえば、合格ラインが100点満点中60点の場合、現在の得点が40点なら、20点分の底上げが必要になります。このギャップを把握することで、今後の学習計画が立てやすくなります。
1-4. 「テキスト→問題集」を何周かする
テキストを読み、問題集を解くというサイクルを1回で終わらせず、何周か繰り返すことが基本です。もちろん、1周で十分な手応えがあれば終了しても構いませんが、通常は繰り返すことで記憶が定着し、理解も深まります。たとえば、合格ラインが60点の試験で、問題集で毎回70点以上を安定して取れるようになれば、ひとまず合格できるという安心感が得られるはずです。
ただし、2周しても得点が伸びず、合格ラインに届かない場合は、使っているテキストや問題集が自分に合っていない可能性もあります。そんなときは無理に続けず、別の教材に切り替えるのも一つの手です。
1-5. 経験を整理する(論述試験の場合)
論述形式の試験、特にIPAのプロジェクトマネージャ試験の午後Ⅱなどでは、過去の実務経験をもとに、数千字の文章を手書きで記述する必要があります。準備なしで挑むのは非常に危険であり、自身の経験をきちんと整理しておくことが重要です。
整理の方法として有効なのが、STARメソッドです。
- S
(Situation) :どのような状況だったか - T
(Task) :自分に課された役割や課題 - A
(Action) :どのように行動したか - R
(Result) :その結果どうなったか
このフレームワークで自身の経験をあらかじめ言語化しておくと、論述試験でも説得力のある文章を書きやすくなります。
実際のプロジェクトマネージャー試験の午後Ⅱでは、
もし、プロジェクトマネージャーの実務経験がないならば、
また、市販されている合格論文集の活用もおすすめです。さまざまな区分の過去合格論文が掲載されているため、自分の立場や経験に近い事例を参考にしやすいでしょう。論述試験の副次的なメリットとして、面接の対策にもなります。論述試験の準備は、実務や転職活動にも活かせるのです。
特にプロジェクトマネージャー試験は、エンジニア職に限らず、学生や他職種の方にも有用です。というのも、資格取得そのものが1つの
1-6. とりあえず受ける
一発合格できれば理想ですが、不合格でも得られるものは多くあります。そこで、
実際に試験を受けてみないと、会場の緊張感や自分のコンディション、手書きの分量にどれだけ対応できるかなど、わからないことが多くあります。特に論述式の試験では、限られた時間内でどれだけ書けるかを体感するだけでも大きな収穫になります。
2. スケジュールを立てて守るコツ
続いて、合格に向けた計画を立て、それを無理なく継続するためのコツを解説します。

2-1. 残り日数から逆算して決める
学習スケジュールは、試験日から逆算して立てることが基本です。岩本さんの場合、1カ月前からの準備を行う際には
2-2. なるべく前倒しする
とはいえ、計画通りに進まないのが人間です。だからこそ、序盤にペースを上げて前倒しで進めることが大切です。岩本さんは、途中でモチベーションが下がることに備えて早めに取り組み、スケジュールのバッファを確保するようにしています。
2-3. 時間泥棒と別れる
「時間が足りない」
SNSも同様で、つい時間を取られがちです。たとえば
3. モチベーションを上げるコツ
ここからは、自らの気持ちを奮い立たせ、勉強を継続する秘訣を解説します。

3-1. 合格後の自分を想像する
資格に合格すると、大きな達成感を得られます。そうした
岩本さん自身も、資格取得をきっかけにして未経験からエンジニアへ転職し、アマゾンウェブサービスジャパン社への入社、そしてENECHANGE社でのVPoT就任などを経験。人生が大きく変わりました。
3-2. 悔しさを思い出す(再挑戦の場合)
再挑戦の強いモチベーションになるのが、
不合格はつらいものですが、何が足りなかったのかを正面から見つめ直すことで、次の挑戦の糧になります。悔しさを原動力にする姿勢が、再挑戦には何よりも大切です。
3-3. スタンプ帳を作る(全冠狙いの場合)
複数の資格を取得する場合、スタンプ帳を作るのは有効なモチベーション管理法です。人は、枠があると埋めたくなるもの。
岩本さんは、IPA全冠を目指していたときに実際にスタンプ帳を作り、試験の達成状況を可視化していました。当時は
3-4. 会社の受験料補助制度を使う
会社の受験料補助制度を活用することも、モチベーション維持のためには効果的です。岩本さんの勤務先であるENECHANGE社では、不合格の場合でも受験料を全額補助してもらえる制度があります。この制度を使って
「うちの会社にはそんな制度はない」
まとめ
本記事では、岩本さんの実体験をもとに、



