新時代を生き抜く越境思考 ~組織、肩書、場所、時間から自由になって成長する
- 沢渡あまね 著
- 定価
- 2,420円(本体2,200円+税10%)
- 発売日
- 2022.3.25 2022.3.1
- 判型
- 特殊判型
- 頁数
- 432ページ
- ISBN
- 978-4-297-12629-2 978-4-297-12630-8
サポート情報
概要
過去に答えがない、組織単独では勝てない時代に、新たな“勝ちパターン”を創るには?
これまでの枠組み、常識、しがらみに縛られない「越境」の仕掛け方を、350以上の企業・自治体・官公庁で働き方改革、組織変革、マネジメント変革を支援してきた著者が集大成。
- 組織の枠を越えて働く
- 多様なメンバーの潜在能力を解放する
- 働く景色を変えて価値観の揺らぎを起こす
- 地域の壁を越えて成果を出す
- 垣根をデジタルですっ飛ばす
「いままでのやり方に限界を感じている」すべての人へ。
こんな方にオススメ
- これからの時代に評価されるキャリアをつくりたいビジネスパーソン
- 会社をよりよく変えたい経営者、管理職
- 地域活性や関係人口増に取り組む、行政や地方コミュニティの責任者、担当者
目次
はじめに スタンドアローンからクロスファンクション・クロスボーダーへ
- 越境の意味:3つのハイブリッド
- 「価値観の揺らぎ」により、「気づき」「発見」「学び」を得る
第1章 なぜいま越境なのか? ~必要性、メリット、アプローチ
なぜ越境が必要なのか?
- 「過去に答えがない」「組織の中に答えを求めにくい」「その組織単独で勝てない」時代
- プレーヤーであっても「両利きの経営」のマインドが必要
- スタンドアローンからクロスファンクション/クロスボーダーへ
越境でどのような変化が生まれるか
- 越境のきっかけ:3つの「つながる」
- 越境の12のバリエーション
- 越境の8つのメリット
第2章 複業・パラレルキャリア ~組織の壁を越える
個人にも組織にもメリットがある複業・パラレルキャリア
- 複業やパラレルキャリアが私たちの可能性を広げる
- コラム 複業と副業の違い
- 複業・パラレルキャリアのメリット
- 2つのベクトル:解禁と受け入れ
- 社内(庁内)複業から、越境の「筋トレ」を始めてみる
- 【ケーススタディ】大手情報通信サービス事業者の社内複業事例
- 複業・パラレルキャリアを成功させるための3つの提言――組織に向けて
選択的週休3日制とどう向き合うか
- 選択的週休3日制のメリットとは
- 選択的週休3日制は、進む2極化
- 「幸せな」選択的週休3日制を実現するための5つの課題
第3章 女性活躍/ダイバーシティ推進 ~今いる多様なメンバーの潜在能力ややる気を解放する
ダイバーシティ&インクルージョンの本質とは
- まずは既存のメンバーが正しく活躍できるようにする
- [成長意欲や能力がある]×[ただし制約条件がある]人が正しく活躍できるようにする
- 餅型チームからおにぎり型チームへ
ダイバーシティ&インクルージョンを邪魔するもの
- 女性活躍の問題地図
- 「女性支援」ではなく「女性起点」そして「全員参加」へ
- ダイバーシティ&インクルージョンを阻む10の壁
育休両立期の人材を制約から解放する
- 育休両立期の人材に対する世の中の誤解や思い込み(バイアス)
- 育休明けのスタッフに合わせてチームミーティングの時間を変えたら、メンバー全員が幸せになった
- 育休両立期の人材のポテンシャルと変化
組織と個人がともに成長するための3方向への提言
- ①To:現場のマネジメント
- ②To:経営者や人事部門
- ③To:国や行政機関
第4章 ワーケーション ~働く景色を変えて価値観の揺らぎを起こす
バケーションよりもワーク重視で! ワーケーションのメリットとは
- 越境学習の選択肢としてワーケーションは有効
- 沢渡が実践して体感したワーケーションのメリットや課題
- ワーケーションは最強のチームビルディングプロセス
ワーケーションの4つの観点
- 「いつ」(平日 or 休日)
- 「どこで」(都市部 or 地方/リゾート地)
- 「だれと」(個人 or グループ)
- 「なにを」(通常業務 or 非日常業務)
- ワーケーションは「バケーション」ではなく「ワーク」を軸に捉えてほしい
ワーケーションのデメリットや課題を解消するには
- ワーケーションの5つのデメリットと解消法
- ワーケーションの11の地域課題
ワーケーションをあたりまえにするにはデジタルワークシフトが必須
- ワーケーションの仕事風景(#ダム際ワーキング のシーンより)
- ワーケーションを実施する側は、滑らかに仕事ができるデジタル環境を
- ワーケーション環境を提供する側は、大きなコストと労力をかけずにキャッシュポイントと顧客動線づくりを
サステイナブル(持続可能)なワーケーションに向けての提言
- ①To:企業
- ②To:中央省庁
- ③To:地域(行政や地域の企業など)
ワーケーションの一形態 #ダム際ワーキング
- #ダム際ワーキング とは
- #ダム際ワーキング の実践事例
- #ダム際ワーキング に適する業務
- ワーケーションは道中も大事なプロセス?
- コラム 地方都市は「ラストワンマイル」「ラストワンアワー」のキャッシュポイント創出を!
第5章 地方都市/レガシー組織 ~地域の壁を越える
地方都市/レガシー組織の問題地図
- ①「地方だから」「製造業だから」
- ②横並び主義
- ③下請け思考
- ④前時代的&画一的な地域インフラ
- ⑤職種の定義や仕事のやり方が古い
- ⑥井の中の蛙
- ⑦見えないものを評価しない/お金を出さない
- ⑧他地域から来る人を遠ざける
広がる格差
- 2つの格差が日本国内で進行している
- 立地や企業規模は「不公平」だが、デジタルは「公平」
地方都市の期待と課題
- 地方都市の5つの期待・強み
- 越境を仕掛けて課題を乗り越えていく
越境人材の採用・定着、企業のアップデートをいかに成功させるか
- 地域に就職・転職した人が定着しない、「もの言わぬ大人しい人」になってしまう要因ビッグ3
- 「3つの戦略」を有機的に組み合わせ発展的解消を
- 業種や職種を越境し、ビジネスモデル変革を成し遂げる ~旭鉄工株式会社 木村哲也さん
- 気合・根性型、体力勝負の営業スタイルを変える ~三光製作株式会社 山岸洋一さん(浜松市)
- 地域や職種・業種の越境によるイノベーションを仕掛ける ~株式会社山岸製作所 山岸晋作さん(金沢市)
過疎化の処方箋
- ①ITに投資をする
- ②スキルを育成する
- ③職種そのものをアップデートする
- ④(いままでマイノリティ扱いされていた)若手や女性などにエンパワーメントする
- ⑤外の血を入れる/外に送る
- ⑥外に開放する
- ⑦そのコミュニティを終わらせる
- ⑧「流出させない」対策より、「戻ってきたくなる」都市づくりを
- 脱「製造業マインド」
- 「過疎化は自業自得です」
「自主的転勤族」が流動する前提で都市を再設計する
- 山間部への移住者は、いわば「自主的転勤族」である
- 自主的転勤族が増えるチャンスを活かす4つの行動
- 人口流出が問題なのではない、戻ってこないのが問題なのだ
第6章 DX ~垣根を越えて新たな「勝ちパターン」を生み出す
DXを考えるための6つの観点
- ①デジタルで「すっ飛ばす」
- ②「ペインポイント」を解消する
- ③他人の土俵に飛び込んで新たな価値を出す
- ④いままでとは異なるプレイヤーを起用して新たな価値を生む
- ⑤「ホームポジション」を研ぎ澄ます
- ⑥テクノロジーに合わせてルールを変える
DXを邪魔するもの
- ①業務改善やBPRとの違いがわかっていない
- ②DXに必要なスキルやマインドが未定義
- ③DX推進組織だけに丸投げされる
- ④従来組織(事業部門、管理部門)が動かない
- ⑤既存の業務が安定しているため、DXに対する本気度が醸成されにくい
- ⑥人事部門が変わろうとしない、動こうとしない
- ⑦PoCで終わってしまう
- ⑧社内の温度差が大きい
- ⑨上位層のマインドが変わらない
DXの本質はX
- ①(デジタル)テクノロジーに合わせて×ルールを変える
- ②情報システム部門の得意領域×事業部門や管理部門の得意領域
管理部門や間接業務のあり方を変える
- ①固定的な管理部門は自らの生存リスクを高める
- ②雑務の多さも大問題
- ③事務のプロに事務設計させてはダメ
- ④管理部門間の越境で経営のペインポイントを解消する
- ⑤越境できるファシリテーター型管理部門は希少価値に
- ⑥管理部門こそ越境体験を
DXできる組織になるための6つの提言
- ①言語化能力を高める
- ②デジタル経験を増やす
- ③データリテラシーを高める
- ④事務/間接業務を(とにかく)減らす、なくす
- ⑤景色を変える(越境学習する機会の提供)
- ⑥自社理解を深める
第7章 越境を変革の武器にするために
越境で身につくスキルとマインド
- 経産省の「人生100年時代の社会人基礎力」に照らし合わせて考えてみる
- デジタルワーク/ハイブリッドワークで成果を出すための8つのスキル
- ディスカッションをする経験とスキル
- ディベートをする経験とスキル
- フレームワークを使いこなすマインドとスキル
越境に向いている人、向いていない人
- 越境に向いていない人
- 越境に向いている人
越境の仕掛け方
- 越境して変革できる組織と人になるための3つのシフト
- 越境を仕掛けやすい8つのタイミング
- 大組織と中小ベンチャー企業の越境を
越境を進めるための提言
- 経営層、DX/組織開発推進部門、人事部門への6つの提言
- 現場のマネジメントへの5つの提言
プロフィール
沢渡あまね
作家/ワークスタイル&組織開発専門家。
あまねキャリア株式会社CEO/株式会社NOKIOOアドバイザー/株式会社なないろのはな 浜松ワークスタイルLab所長/ワークフロー総研フェロー。
日産自動車、NTTデータなど(情報システム・広報・ネットワークソリューション事業部門などを経験)を経て現職。350以上の企業・自治体・官公庁で、働き方改革、組織変革、マネジメント変革の支援・講演および執筆・メディア出演をおこなう。
著書は『バリューサイクル・マネジメント』『どこでも成果を出す技術』『職場の問題地図』『仕事の問題地図』『働き方の問題地図』『システムの問題地図』『マネージャーの問題地図』『業務改善の問題地図』『職場の問題かるた』『仕事ごっこ』『業務デザインの発想法』『仕事は「徒然草」でうまくいく』(技術評論社)、『ここはウォーターフォール市、アジャイル町』(翔泳社)、『はじめてのkintone』『新人ガールITIL使って業務プロセス改善します!』(C&R研究所)ほか多数。
趣味はダムめぐり。#ダム際ワーキング
『沢渡あまねマネジメントクラブ』(オンラインサロン)
https://lounge.dmm.com/detail/3624/index/
『組織変革Lab』(法人・行政向け、オンライン越境学習プログラム)
https://cx.hamamatsu-ws-lab.com/
ホームページ:http://amane-career.com/
Twitter:@amane_sawatari
Facebook:https://www.facebook.com/amane.sawatari
メール:info@amane-career.com
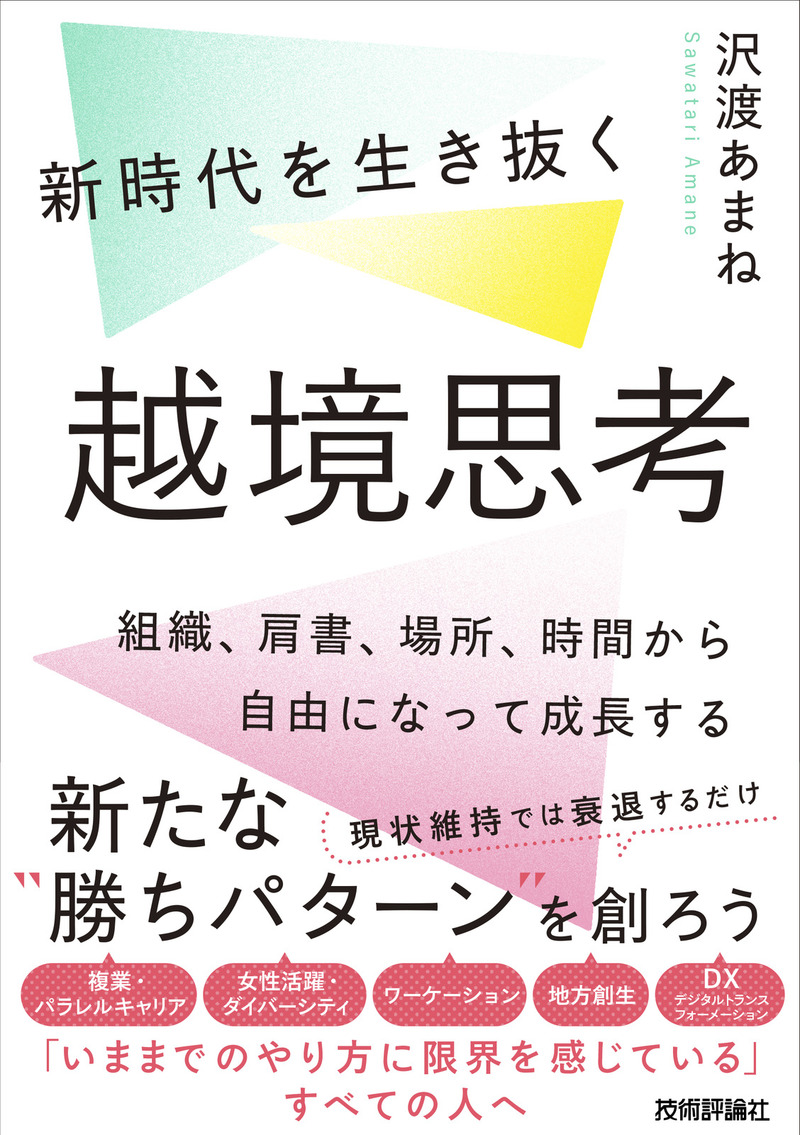
著者の一言
スタンドアローンからクロスファンクション・クロスボーダーへ
組織や地域を越えて人と人とがつながり、既存の問題や課題を解決する、あるいは新たな価値を生むにはどうしたらいいか?
越境――本書はこのテーマに向き合うべく生まれました。
「いままでのやり方に限界を感じている」
みなさんの多くがそう感じていることでしょう。その停滞感や危機感は、企業組織も持ち始めています。筆者のもとにも、連日のように企業、行政機関、メディアなどから「組織風土改革」「組織変革」「イノベーション」「DX」「コミュニケーション」を冠した相談や取材依頼が寄せられています。日本の大企業はこぞってイノベーションやDXをはじめとするトランスフォーメーションを指向するようになりました。
ところが、これがなかなかうまくいかない。
「経営陣は口先ばかり。イノベーションもDXもまったく進まない」
「意見や提案をしようとしても、上につぶされる」
「目先の成果が出る仕事しか評価されない」
「イノベーションを仕掛けたい。しかし、そもそもどこに声をあげたらいいのかわからない」
「社内の組織が縦割り。管理部門が突然横から出てきて、待ったがかかる」
「社内の“変わりたくない”抵抗勢力に足を引っ張られる」
このような切ない声が、つねに日本の職場にこだましています。
私はワークスタイル・組織開発の専門家として、これまで350を超える企業・自治体・官公庁(以下「企業組織」と総称)の現場のリアルに向き合ってきました。イノベーションが進まない。それどころか、目先の仕事の業務改善すら進まない。その背景には、いま述べたようなリアルがまちがいなく存在します。いわゆる大企業病のジレンマです。
日本の組織の倦怠感と停滞感。どこから風穴を開けるか?
どのようにして大企業病を脱していくか?
その答えの1つが越境です。
越境の意味:3つのハイブリッド
「越境とは3つのハイブリッドを乗りこなすことである」
筆者が組織開発やイノベーションがテーマの講演で強調しているメッセージです。自組織単独(スタンドアローン)で問題解決や新規価値創出がしにくい時代、3つのハイブリッドを乗りこなすことのできる組織や個人は強い。その3つとは、場所のハイブリッド、顔のハイブリッド、組織のハイブリッドです。
①場所のハイブリッド
我が国においても、テレワークの浸透にともない、働く場所がハイブリッドになりつつあります。先進的な企業では、フルリモートワークなど事業所に出社しない働き方を取り入れ、他地域の人材を獲得するスタイルも増えてきました。ワーケーション(ワークとバケーションを組み合わせた新たなワークスタイル)のような、オフィスでも自宅でもない場所(サードプレイス)で成果を出すスタイルも注目されつつあります。
事業所(オフィス、工場、店舗など)、自宅、コワーキングなどのコミュニティスペース、カフェ、移動や合間のクルマの中、リゾート地、ダム際……場所にとらわれず成果を出せる、あるいは場所が異なる人とつながって仕事をできるマインドとスキルを兼ね備えておくと、これからの時代まちがいなく強いでしょう。
②顔のハイブリッド
顔のハイブリッド化も進みつつあります。もはや生え抜きの正社員オンリーで事業を回している組織は、事業継続性の観点からもリスクがあると考えられるかもしれません。複業(パラレルキャリア)や選択的週休3日制なども進みつつあります。
少子高齢化による労働力不足が深刻化する時代、週5日×8時間以上その組織にフルコミットできる人だけに拘っていては、人材の獲得や維持も難しくなります。組織は、複業人材、フリーランス、顧問など単一組織だけに属しているわけではない人材、すなわち複数の顔を持つ人材を活用できるようになっていく必要があります。もちろん、働く個人(我々)も、複数の組織で仕事をするためのマネジメント能力やスキルを身につけていく必要があります。
複数の顔を持つ人と仕事をするために、組織は制約条件をなくしていかなければなりません。「すべて対面で」「出社して」「自社独自の業務プロセスやコミュニケーションプロセスに合わせさせて」では、複業人材は活躍できません。個社個社のガラパゴスな事情に合わせていては、そのためのコミュニケーションの労力と稼働で複業人材は潰れてしまいます。組織サイドの業務の標準化、デジタル化、スリム化が求められます。
③職種のハイブリッド
業界や職種のハイブリッドも急速に進んできています。FinTechは金融×ITのハイブリッド、AgriTechは農業×ITのハイブリッドです。業界や職種を越境することで既存の問題・課題を解決したり新たな価値を生むコラボレーションと捉えることができます。HRTech(人事領域×IT)のように、職務領域のハイブリッドによるイノベーションも生まれてきました。
掛け合わせる相手は、IT(Tech)だけとは限りません。神姫バス(兵庫県)は農協とコラボレーションし、貨客混載を実現。地方都市の高齢化および過疎地域における農業生産者の問題の解消に取り組んでいます。バス事業者、農協、農業生産者および行政の「異業種越境プロジェクト」と捉えることができるでしょう。
思い起こせば、私自身も多かれ少なかれ越境を重ねてきています。
日産自動車(海外マ―ティング部門)在職中は、ルノーを含むグローバル体制のマネジメントの下、海外130か国の販売統括会社の責任者や担当者と議論しながら物事を進めていました。
NTTデータに転職した2008年頃からは、テレワークを試行。オフィスと自宅や帰省先で仕事をするスタイルを経験し始めました。海外(中国)にサポート拠点を立ち上げ、自担当の業務を日本と中国の2拠点で運営する体制に。「場所のハイブリッド」(国や文化のハイブリッドも)が加速しました。
2014年9月に企業勤めを終了し、フリーランスに(2021年8月に法人化)。ここから「顔のハイブリッド」が加わります。自らの事業を運営しながら、NOKIOO、なないろのはな(浜松ワークスタイルLab)、エイトレッドなど複数の企業に、顧問、取締役、事業責任者として参画。その他、数多くの大企業のプロジェクトにアドバイザーとして関わってきています。
職種のハイブリッドも進んでいます。2021年6月に、浜松の地域企業であるWe will代表 杉浦直樹さんと組んで「デジタルワークシフトコンソーシアム浜松」を発足。KDDIまとめてオフィス中部、Box Japan、日本シャルフKDDIまとめてオフィス中部、Box Japan、エイトレッド、日本シャルフ、弁護士ドットコム、および浜松市が加わり、地方企業のデジタルワークシフトとマインドシフトを推し進めています。これは、地域のベンチャー企業、大企業、行政の越境の取り組みと考えることができるでしょう。
https://dwsc.jp/
私個人のライフワークとしては、#ダム際ワーキングを実践および推進しています。ダムおよび近隣のカフェや宿泊施設などで仕事しつつ、自然の中でリフレッシュする新しい働き方。ダム巡りが好きな私は、2009年頃からたびたびダム際で仕事をしています。個人作業や執筆活動はもちろん、クライアントや編集者とつないでWeb会議したり、オンラインのトークイベントを配信したりと、企業間のコラボレーションもダム際で起こりつつあります。本書執筆時点で、川根本町(静岡県)と連携した大井川流域の#ダム際ワーキングプロジェクトも進行しています。私が個人で始めた取り組みが、新たな地域活性モデル、ビジネスモデルに昇華しつつあります(#ダム際ワーキングの様子と効果は、第4章(ワーケーション)でくわしく解説します)。
https://damworking.com/
「価値観の揺らぎ」により、「気づき」「発見」「学び」を得る
越境を通じて気づきや学びを得るプロセスを、越境学習といいます。特定非営利活動法人しごとのみらい代表 竹内義晴さんは、インタビュー記事で越境学習を次のように説明しています。
また、越境学習の権威である法政大学大学院政策創造研究科 教授の石山恒貴さんは、経済産業省のインタビュー記事(越境学習によるVUCA時代の企業人材育成)でこう述べています。
つまり、こう考えることができます。
たとえば、本書でも解説するワーケーションや #ダム際ワーキングは、価値観の揺らぎが起こりやすい学習の手段の1つと捉えることもできます。普段とは異なる交通手段で、普段とは異なる景色を見ながら移動し、普段とは異なる土地で、普段とは異なる行動をする。たとえ1人での行動であっても、あるいはチームメンバーなどいつもと同じメンバーとであっても、景色の変化が多かれ少なかれ揺らぎをもたらします。それが、集中力を高めたり、新しいアイディアや発想を生んだり、ディスカッションを生みやすくするのです。
「越境で何を解決するか?」
「どこから越境を仕掛けていくか?」
「越境の考え方を自組織にどうインストールしていくか?」
本書がその道しるべになれば幸いです。