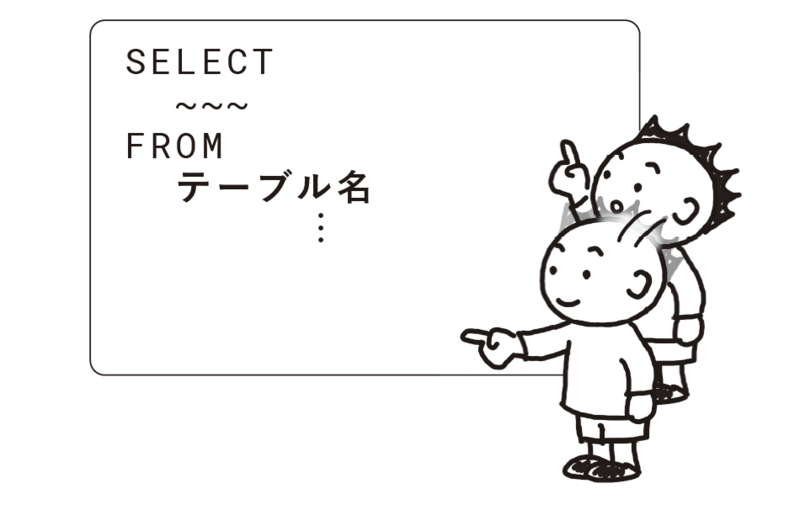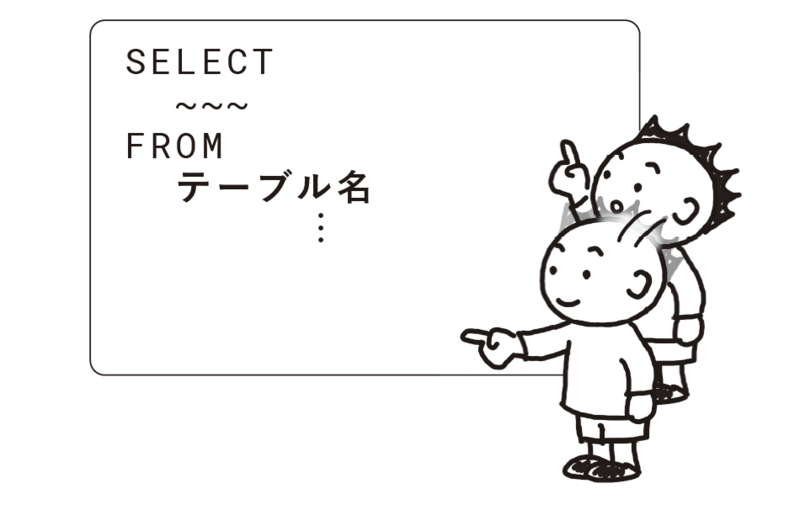生成AIの発展が著しい現代、さまざまなスキルが、これからはAIに取って代わられるので不要になるのではないかという声があります。データベースを操作する言語であるSQLもその1つです。しかしいつの時代のビジネスでも複式簿記が基礎教養であるのと同様に、データという存在の重要性がますます高まる中、SQLは21世紀の複式簿記とも言える基盤技術としての地位を確立しつつあります。2022年度から高校の必修科目「情報I」でリレーショナルデータベースとSQLが扱われるようになった事実は、この言語の重要性を教育面からも裏付けています。
「書き順」という概念
かつてSQLに関する入門書では、「SQLはStructured Query Language(構造化問い合わせ言語)の略です」という説明がありました。現代では、SQLは略語では単なるSQLというひとつの名称ということになっていますが、この「構造化」というのは非常に含蓄のある表現です。SQLは順番に手続きを書くものではありません。欲しい結果になるように、構文に沿うようにして各機能のブロックを組み立てて1つのSQL文を作っていくという形になります。このときの、何をどう組み立てるか、というのがSQLの構造になります。この構造の組み立て方を思考の手順として明示するものを「書き順」と考えることができます。
構造化に則ったSQLの「書き順」では、1つのSQLを単に頭から順番につらつらと書いていくケースは皆無です。1つのSQLを書き上げるために下に飛んだり上に戻ったりを繰り返します。
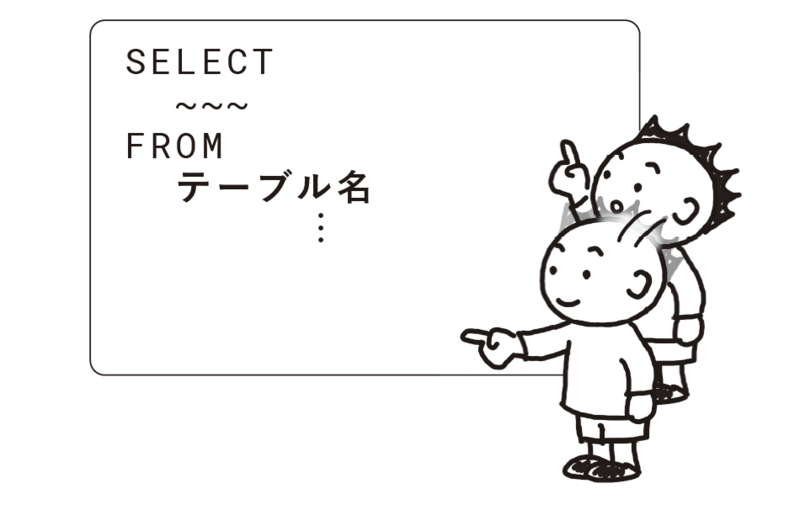
思いつきでデタラメに書いた字は汚いものです。正しい筆順を知りそれを実践することで、達筆ではないにしても誰でも当たり前に読んでもらえる字を書くことができるようになります。SQLも同じです。SQLの読み手であるRDBMSに対して、書き手の意図がしっかりと伝わるように書くことが大切です。
そして、この書き順を徹底するための重要な手段は「改行の多用」です。改行を多用したSQLは、最初のうちは冗長に感じるかもしれません。しかし改行がもたらす思考への効果は絶大です。どんなときでも書き順を意識してSQLを書いているうちに、現場でどんな複雑な問題に出会っても、何をどう書けばいいのかが頭に閃ひらめくようになり、そしてすらすらと手が動くようになるでしょう。
データ活用が不可欠な現代社会において、SQLの書き順を習得することは、単に技術を学ぶ以上の意味を持ちます。それはデータと対話するための思考法そのものを身に付ける行為であり、AI時代においても変わらず価値を持つ普遍的なスキルとなるでしょう。
『改訂第4版 すらすらと手が動くようになる SQL書き方ドリル』は、SQLの書き順をマスターするための考え方を身につけるための解説と豊富な問題満載の書籍です。