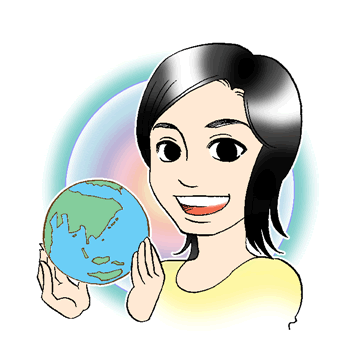東京・お台場にある科学館、日本科学未来館。宇宙飛行士の毛利 衛さんが館長を務めていることでも有名です。今回の対談相手は、日本科学未来館に勤務している「おねえさん」岡野麻衣子さんです。
岡野麻衣子(おかのまいこ)学生時代の専攻:生命科学。北里大学大学院医療系研究科博士課程終了。医学博士。博士課程在学中より、日本科学未来館にてインタープリターとして勤務。フロア解説員を経て学校への訪問講義や学校を中心とした地域連携活動等のイベントを行う。現在は、館の運営業務を担当。
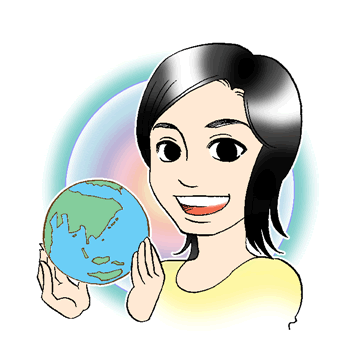
ASIMOと毛利さんに魅せられて
“一般の方々に科学を教える”サイエンスコミュニケーターとして、内田の先輩である立場の岡野さん。名刺には“医学博士”の4文字が……
岡野「ああ、それは事情がありまして。私は北里大学に衛生学部の存在した最後の代の生徒なんです。博士課程に進学したタイミングで、今までの理学部系列の大学院から医療系全般になったので、肩書きは“医学博士”ですが私の専攻は生物科学科です」
――なるほど、ちょうど移り変わる時期だったんですね。
岡野「はい。その改編の関係から、普通は大学院の博士課程は3年ですけど、私は4年でした」
――博士4年生の頃から、非常勤として日本科学未来館(以下、未来館)でインタープリター(解説員)の仕事をしていたのですよね。博士課程最後の年に、非常勤として勤務とはハードだったかと思うのですが……。
岡野「ええ。ちょうど過去3年間の研究のラストスパートをかけようというときだったので、教授に非常に怒られました。でも“土日しか行かないし、研究には絶対支障をきたさないから”と説得してお許しをもらいました」
――教授を説得してまでも、とは岡野さんの並々ならぬ熱意がわかりますね。その“未来館のインタープリターになりたい!”と思われるきっかけは何だったのでしょうか?
岡野「実は、オープンしたばかりの未来館を背景に、宇宙飛行士である毛利さんとASIMOが握手するシーンを見て、感動しまして。その番組を観て数日後、新聞にちょうど未来館の職員募集の広告が出ていたので、応募してみました」
――感動した数日後に募集広告……絶妙のタイミングですね。
岡野「いえ、これが博士3年の3月の話だったのですが、私はてっきり次年度からの職員募集だと勘違いしていました。ですが、翌月4月からの勤務が条件だったんですね。やむを得ず非常勤という形にさせていただきました」
――そこまでしても、未来館に勤務したい、と惹きつけられるということは、もともと科学館や博物館が好きだったんでしょうか?
岡野「確かに博物館はもともと好きでよく行ってましたね。あと、私の実家が鹿児島なので、種子島の中継の横で、ロケットが実際に飛んでいる、という様子を見て育ちました。宇宙飛行士になりたい、毛利さんに会いたいという気持ちがすごくありました」
――まさかその憧れの毛利さんと一緒にお仕事できるなんて……! というお気持ちですよね。
幼少時に憧れていた人とお仕事できているなんて羨ましい! と単純に思ってしまいますが、そこに至るまでは紆余曲折があったようです。
大学4年まで苦手だった生物
――小さいときから理科や科学はお好きでしたか?
岡野「昆虫採集はしていました。屋久島まで行って、そこでしか捕まえられない蝶を追っかけたこともあります」
――贅沢な環境ですねー。だいたい理系に来る人は、おおざっぱな分け方ですが、“星”か“メカ”か“昆虫”から入りますよね。
岡野「それで考えると私は特に昆虫からですね。蝶が大好きで」
――昔から生物がお好きだったんですね。
岡野「でも、それも小学校くらいまでです。中学、高校だと受験勉強があるので、生き物に興味を持つような時間もなくなりました。そのうち生物の授業を受けても、まったく、まったく、まーったく! わからなくなり、それで嫌いになっちゃいましたねえ」
――“まーったく!”ですか(笑)! 小さい頃好きだったはずの分野が嫌いにまでなっちゃったんですか?
岡野「生物は本当に苦手でした」
――でも、岡野さんは生物科学科のご出身ですよね?
岡野「化学で受験したんです。化学や数学は好きでしたけど、生物が本当に苦手で。だって“核の中に染色体があります”なんて教科書に書かれていても、見えないじゃないですか。その上、それが二重らせんを巻いているなんて言われても…イメージがわかなくて」
――それでも、生物科学科にご入学されたと。
岡野「当時は“バイオテクノロジー”という言葉が少しずつ浸透してきた頃でした。私にとっては非常にこの言葉が魅惑的でして。生物を扱う研究分野として、とても魅力的でかつ斬新なことができそうというイメージがあったんです」
――入学後は苦労されましたか?
岡野「1年のうちは教養科目ばかりだからまだ良かったんですけど。2年で実習が始まってからが辛かったですね」
“まったく”という言葉を繰り返し使って強調する岡野さん。うーん、本当に生物が苦手だった模様。しかしながら勉強せざるをえない状況に……すると、学士卒業間際になる頃に、その面白さに目覚めたと言います。
岡野「4年で卒業研究をするときになって、研究の面白さが初めてわかったんです」
――そのきっかけは、どんなことがあったんでしょうか?
岡野「実験です。実験は実習と違って、自分1人でやらないといけませんから」
――なるほど。卒業実験で1人で全部やることで理解されたんですね。これは、調理実習で作り方の一部だけを習っても、その料理そのものを作ることはできないことと似ているかも!
岡野「そうですね。実習のように“ここの一部分を一生懸命やりました、ハイおしまい”だと、つながりは全然わからないですよね。実験を1人で行うことで、そのつながりが理解できて、それから面白くなりました」
――研究室ではどんな実験をされていたんですか。
岡野「4年生の卒業研究ではES細胞を飼っていました。あれは本当に飼うのが大変で。すぐ機嫌悪くなって死んじゃうんですよ、なので毎日声かけてましたね“おはよう、元気?”とか」
――わ、なんかそれは楽しそうでいいですねえ。
岡野「キムタクっていう名前をつけてたんですよ。木村拓哉さんは別に好きじゃないんですけど、なんとなく。そうすると、だんだん愛情がわいてきて…」
――今日もキムタク元気だなとか(笑)
岡野「そうそう(笑)。ES細胞を飼っていたときは一番神経を使いましたね。ですが、次の日に見ると本当に心筋や神経になっていたりするんですよ。感動するし、生きてるんだなあ、と実感できる。見えると実感できるけど、見えないとなかなかわからないですよね」
――生物が苦手になったきっかけからもそうなんですが、自分の目で確かめて“心から納得するまで気がすまない”というところが理系っぽいなあと。研究者マインドですよね。
ところで、修士から博士に進学する間で迷いはありましたか?
岡野「ありませんでした。というのも、修士1年目は慣れるのが精一杯で、自分の実験がほとんどできなかったんです。結果がクリアではないモヤッとした修士論文になってしまったので、これは明らかにしないと嫌だなあ、と」
――なるほど。やはり納得するまで気がすまないタイプなんですね。
岡野「あと、大きかったのは修士発表ですね。発表前日に研究室でプレゼンしたときに…先輩や先生から散々注意されて。“何て自分はまとまってないんだろう!”ということをそのときに初めて気付いたんですよ」
――よりによって修士発表前日(笑)。もっと前に指摘してくれれば…でも、気付かせてくれるなんてありがたい先輩たちですよね。
岡野「“これだけ実験しましたよ”と言うことは誰にでもできる、でも、それをロジカルにまとめて、なおかつ発表しないと、自分以外の人には伝わらない。自分は何も筋道をわかっていなかったと気付いてすごく恥ずかしかったんです。リベンジせねばと」
自らが納得いくところまで進めたいと考える岡野さん。そして、気が付けば苦手だった生物で博士課程まで進学することに。
日本科学未来館

研究者からいきなりインタープリター(解説員)に
博士課程の途中から、日本科学未来館に非常勤で働き始めたというのは冒頭の通り。研究者と解説員、仕事の内容は大きく異なるように思えるのですが…
――そこまで研究を熱心にされていて、いきなり未来館にいくという発想はあまり思いつかないのですが。研究職に就くというご希望はなかったんですか?
岡野「同じ研究室や研究室系列の企業であったり、やっぱり就職先が限られてしまいますよね。そうするとまたあまり変わらない生活になるんじゃないかと思ったんです。研究室にずっといると人間関係も考え方もすごく狭くなってしまうじゃないですか。研究室のメンバーとは、飲みに行っても“タンパク質がどうの…”といつも同じ話になってしまう(笑)」
――ちょうどそんなことを考えているときに、タイミング良く毛利さんがテレビに出てきたと。
岡野「はい。それに、感動したことも大きかったのですが、研究することの意味について考えていた時期でもあったので。母親に“大学では何の研究をしているの?”と聞かれたので、説明しました。そうしたら“何を言っているのか専門すぎて全然わからない!”とばっさりと言われて。逆にすんなり理解されても、それは研究としてどうなんだろう、とも思いますが」
――説明はなかなか難しいですよね、特に自分の専門分野だと。
岡野「そうなんですよね、研究室や学会内って普通の人が聞いてもわからないことをやっていて、その中で発表し合う。私の場合は、どうしても自己満足に陥りがちでした」
――“普通”の感覚がわからなくなってきますからね。
岡野「うちの教授は“海外では科研費を申請するときにマンガを描くんだ。マンガのようにどれだけわかりやすく説得するかが重要なんだ。それでないと自分達の実験費はとれないんだ”と言っていました」
――それはごもっともですね。私の担当教員は“どんな専門家でも、専門外のことはわからない。だから中学生に説明するつもりで”がモットーでした。わかりやすく説明しなければ、研究の必要性がわかってもらえませんものね。
岡野「私はそれを聞いたときから、研究というのは、きちんと報告書を出して、その報告書がどういう形であれ社会に浸透しないと意味はないという考えを持つようになりました。ですので、科学の現場=研究をきちんと社会に伝えるという意味で、未来館はすごく魅力的に思えたんです」
専門分野だからこそ、見えていないこと
こうして、学生時代から未来館で働き始めた岡野さん。非常勤から常勤のインタープリターを経て、現在は運営業務室で全体の調整を行っています。
――学生時代の専攻は、今、現場でどのように活かされていますか?
岡野「……ないんですよ(笑)。展示物を解説する立場になると、いかに一般の人にわかりやすく説明できるかが重要。そういった場合、逆に専門でなかったインタープリターのほうがわかりやすく説明できるんです」
――具体的な例を挙げると?
岡野「お客さまから“ゲノムって何ですか?”と聞かれたときに、研究生活でゲノムと遺伝子を区別して使うことなんてほとんどなかったので“私、説明できない!”となっちゃって」
――生物が分野外の私だからその二つをきちんと説明しろと言われると難しいかと思ったのですが、ご専門だからこそ、というのはあるんでしょうね。
岡野「お客さまが必要としているのは、言葉の定義だということが、そこでわかりました。ゲノム、遺伝子、DNA、染色体…全部を一緒くたにして考えていて、専門分野ではそれで通じるのかもしれないけど、そこをきちんと理解してもらえない限り、一般の方には興味を持ってもらえない」
――なるほど、言葉の定義って大事なんですねえ。いま、お話を聞きながら自分に近い分野として“エネルギー”や“仕事”の説明を考えていたんですが。定義を言っても仕方ないのかな、と思ったらそうではないと。
岡野「生命科学は特にそうなんですよ。だから私も高校のときに“染色体ってなんなの?”“なんでヒストンに巻かれてるの?”とかということを疑問に思ったのかなと。イメージができないんですよね。知っていることを言うだけじゃいけないんだ、と気付いたこの体験は、自分の中ではとても大きかったです」
――なるほど。岡野さんは大学4年まで納得いかない思いをされていたからこそ、その過程が活きているのかもしれませんね
岡野さんオススメ展示 その1:有人潜水調査船「しんかい6500」
水深6,500mまで潜ることができる潜水調査船で、現在運航中の有人潜水調査船のなかでは世界で一番深く潜ることが可能。では、なぜ「6,500m」なのでしょうか?世界一を目指したからでしょうか?その理由は未来館で聞いてみよう!

理系に求められるコミュニケーション能力
日本未来館のインタープリター採用条件は、理系大学の修士卒以上。今の理系のインタープリターに必要なのは、コミュニケーション能力だとか。
岡野「正直私は、コミュニケーション能力があったら、採用条件の学歴を満たさなくても良いのではと思っているんです」
――先ほどおっしゃったように、専門分野を知りすぎていると逆にコミュニケーションがとりにくくなってしまう傾向はありますよね。
岡野「常連のお客様からよく言われますよ、インタープリターは高飛車だと。“知ってて当然でしょう?”という目線で話している印象を与えてしまっているみたいなんです」
――と、言いますと?
岡野「例えばスーパーカミオカンデの展示を説明するときに、“(展示を指して)これが、スーパーカミオカンデです。ニュートリノを検出する装置です”と説明するよりも、“この装置をつくった小柴昌俊さんはアイスクリームが好きらしいですよ”と、“人”から入ると、ああそうなんだ、と聞いてもらえます」
――なるほど。いきなり“これが”と核心の専門のことを言われても、知らない人にはピンとこないですよね。
岡野「ええ。人によりけりでしょうけど、もともとわからないものなのに、これがそうなんだ、って言われても、相変わらずわからないですよね」
――“アイスクリームが好きらしい”というところから入るのはお上手ですね!
岡野「何度も解説にチャレンジしながらお客様と対話することが未来館で学んでいくスキルだと思いますね。何度も玉砕しますから。やっぱり怒られるんですよ、お客さまに。そんなんじゃわかんないよ!って」
――たくさんの方が1日にいらっしゃいますもんね。しかも、小学生から知識豊富な大人までと、年齢も知識もバラバラで。
岡野「はい、研究者の方も結構お見えになりますよ」
研究者にも他分野を知ってほしい
一般の方はもちろんのこと、研究者の方も積極的に他分野の展示を知って欲しいと言います。それにはこんなエピソードが。
岡野「一番最初に未来館の展示を見て驚いたのは、先端の科学技術の中で、知らない展示が多かったということです。恥ずかしながら、先ほどのスーパーカミオカンデの名前すら知りませんでした」
――岡野さんにとっては、分野が異なりますから、当然のことかもしれません。
岡野「研究生活を長く続けていると、自分達の分野が一番だと思ってしまう傾向がある。現に私もそうでした。でも、他の分野で何をやっているのかも知らないくせに、それは何ておこがましいことだろうと」
――専門どっぷりだと、良くも悪くも、まわりが見えなくなってしまいますものね。でもそこで“他の分野を知らない自分はおこがましい”と考える岡野さんは素敵ですね。
岡野「スーパーカミオカンデの開発にかける想いを聞いたときには、圧倒されて鳥肌が立ちました。いろんな分野の考え方を研究者は知るべきだと思いましたね。その研究者自身がどういう想いでこれを作っているのか、倫理観、歴史観、世界観…これを知ることはすごく大事だと思うのです」
――特に岡野さんの専攻されていた生命科学では、倫理観も重要になってきますね。
岡野「はい、ES細胞の研究だけに没頭していると、命や生を実験対象としてしか接しなくなることがあります。そこには必ず倫理的要素がないと怖いことになってしまう。研究者は、いろんな分野の考え方を知って、知的好奇心とタブーの線引きができないと」
――この“知的好奇心”と“タブー”の線引きって、本当に難しい話で。でも、他分野の話を少しでも知るだけで、研究者自身もその線引きがうっすら見えてくるのかもしれませんね。
展示「スーパーカミオカンデの世界」
「謎の素粒子」ニュートリノを検出する装置、スーパーカミオカンデ。ここでは、スーパーカミオカンデのメイン部分、光電子増倍管の原寸大モデルを展示。さらに10分1モデルの中に入り、ニュートリノが与える反応現象によって生まれた光を体験することができる

理科離れ・理科教育…思うことは
日本科学未来館では、学校や教育機関と連携した活動のモデル開発と普及活動を行っています。去年まではそちらも担当されていたという岡野さん。
岡野「文部科学省は、学校が校外と連携することを推進しているけれど、先生はどこで何をすれば良いかわからない。そこで、学習の一環で未来館を利用を検討してもらったんです」
――子ども達にワークシートを書かせたり、といったことでしょうか?
岡野「はい。このワークシートが重要で。難しいことを書くようにしても無理なので、1行でも答えが成立するような簡単な質問をいくつか並べて、つなげると自動的にプレゼンできるような内容にしていました」
――なるほど、うまく誘導されているんですね。“できた”という達成感は子どもにとって大きい。
岡野「やれた!という自信になりますからね。あと、プレゼンの後に、意見ではなく良かった点を述べて、褒めさせるようにしたんです。そうするとすごく良い雰囲気のまま帰っていく。こうして生徒が変わると先生も変われる」
――生徒もさることながら、先生を変えることも重要かもしれませんね。
岡野「はい、生徒は意欲もあるし必要なものに対しては敏感です。先生の興味をどれだけ引き出すかのほうが課題なんだと思います」
――子どもと親の関係と一緒ですね。親が興味のないことに子どもが持つわけはないんですよ。“頑張って勉強しなさい!”だけ言っても、効果はないのと同じでしょうね。
岡野「今年、小学校の教員研修に行って痛感しました。小学校の先生というと、1人で全科目を担当しないといけないけれど、必ずしも理系である必要はないですよね」
――そうですね。むしろ文系出身の方が多と聞きます。
岡野「すると、理科の実験ができないんですよ。マッチがすれなかったり、金網の表裏がわからなかったり。“怖くてできない”と言う先生もいました」
――えー!さすがにそれは児童にとって困りますよね。
岡野「先生が怖がっていたら、児童にもそれが伝わっちゃいますよね。子どもの理科離れと言われていますが、先生の影響も大きいと私は思います」
必要なのは、判断力と理解力
――小学校以外にも、中学・高校の視察も行っていらしたとのことですが、生徒さんを見て何か思うことはありますか?
岡野「レベルはすごく高いです。高校生なのに英語でプレゼンもしちゃう。天才だ!って思っちゃうくらい。けれども、そのようなスキルよりも“将来は何になるのか”を考える時間を与えたほうが良いんじゃないかなと思いますね」
――大学入学“だけ”が目標になってしまうと…
岡野「本当にできの良い生徒さんたちが伸び悩むのは、もったいないと思います。あと、学校で求められていた勉強のできる人と、社会でデキる人って絶対違う! そういうことを教えないと」
――実際、そうですよね。学習指導要項の“生きる力”というのは、そういうことを教えることを目指していたように思っていたんですが……。
岡野「私が思うに、“生きる力”はそのとき自分はどうするか? と判断する力と、今の自分の立ち位置はどこか? と理解する力かと。
ディベートはそういう意味ですごく良い訓練じゃないでしょうか。自分の立場を設定されて、最初は仕方なくても段々その気になってくる。立場を明確にしないまま、良い・悪いをぼやかしたまま、納得いかないまま進めていくと、後であれっ? と思うことが起きてしまいますからね」
――岡野さんがそう思われるのは、研究室時代での教授とのやりとりを通じてでしょうか?
岡野「そうかもしれないですね。こうなりたいと思うからには、自分がどういうロジックで進めるか、考えた上で進めないといけない。そうしていくことで自分も納得できる」
――研究室に恵まれてましたね。これは理系出身だからって、必ずしも身につくことではないですから
岡野さんオススメ展示 その2:セラピー用ロボット「パロ」。
世界一の癒し系ロボットとして、ギネス世界記録にも。「日々落ち込むこともありますが、そんなときは触りにいきます。つぶらな瞳がとってもかわいいです!!」とのこと。実は、職場のPCの壁紙も「パロ」だそうです。

コミュニケーション現場における理系女性とは?
――ところで本企画の大テーマなのですが…岡野さんの考える“理系女性”とは?
岡野「…考えてみると、理系女性と文系女性の違いってほとんどないのかな。むしろ、サイエンスコミュニケーションの現場って文系に近いですし」
――確かに近いですね、というか両方の要素が必要とされている気がします。
岡野「どれだけ相手の話を引きだせるかというのは、文系理系問わず、何系だから得意!ということはないですよね。
でも、“理系女子”というイメージは確かにありますよね。ついでに“理系男子”も」
――あえて“理系女子”イメージというと?
岡野「うーん、文系の友だちと話している内容を思い返してみると、彼女たちの悩みの多くは人間関係、でも私は仕事。そこが違うのかな。
文系方の悩みは、人間関係をどうスムーズにするか、そしてその人達とどう”平均的に”なれるのか。気にならなくはならないけれど、理系の人ってそういうことにあまり気遣わないかもしれないですね。個性が強い人のほうが多い気はしますよね」
――理系を選択した時点で、平均的ではない志向、個性の強さがあるのかもしれないですね。
岡野「理系は、もともと何かなりたいものがあって選択する人が多いですからね。文系でも、そういう人達はまたちょっと違うのかもしれないですよね」
――あえてマイノリティの道を進んでいるわけですから。今よりも数の少なかった“理系女子”という枠組に入っていく、ということは自分を振り返っても“やりたい何かがある”じゃないとわざわざ選択しないのかもしれませんね。
(2009年7月対談収録)
対談を終えて
サイエンスコミュニケーターとしての大先輩である岡野さん。インタビュー中の応対も、論理的で説明がわかりやすい! これは研究室で“ロジック”の大事さに気づかれたことと、日本科学未来館でインタープリターとして鍛えられた経験の双方から来るものなのでしょう。非常に熱心にお仕事に取り組まれていることがわかる一方で、肩肘を張った感じがない。同性でも憧れてしまう素敵な女性でした。
インタビュー後は、共通の「趣味」の話題で盛り上がったのですが……内緒にさせていただきます!
(イラスト 高世えりこ)
※ 記載画像の無断転載・改変等はご遠慮下さい。
- プロフィール
岡野麻衣子(おかのまいこ)
学生時代の専攻:生命科学。
北里大学大学院医療系研究科博士課程終了。医学博士。博士課程在学中より、日本科学未来館にてインタープリターとして勤務。フロア解説員を経て学校への訪問講義や学校を中心とした地域連携活動等のイベントを行う。現在は、館の運営業務を担当。