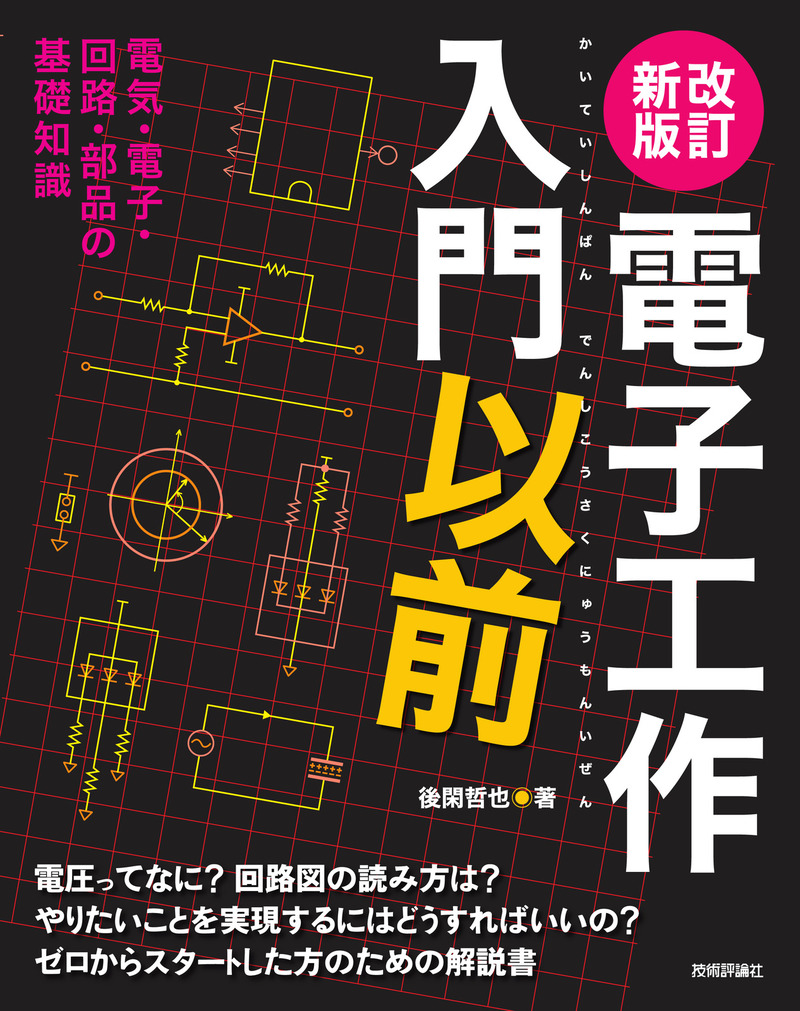改訂新版 電子工作入門以前
- 後閑哲也 著
- 定価
- 2,860円(本体2,600円+税10%)
- 発売日
- 2025.8.26
- 判型
- B5変形
- 頁数
- 328ページ
- ISBN
- 978-4-297-15070-9 978-4-297-15071-6
概要
「電子工作を始めたいけど、何から手を付けたらいいの?」
高性能なマイコンボードが普及し、電子工作へのハードルは下がったはずなのに、「本やWebの通りにしか作れない」「はんだ付けも怖いし回路図もチンプンカンプン」「オリジナル作品は夢のまた夢」と、次の一歩を踏み出せないでいませんか?
ご安心ください! 本書は、そんな「入門以前の知識を知りたい」あなたのための決定版です。まず電気・電子の発見の歴史を追いながら基礎知識を学びます。次に回路図の読み方や、抵抗・コンデンサなど基礎的な部品の役割・選び方を解説。さらには「光らせる」「音を出す」「モーターを動かす」といった「作って楽しい」を実感できる電子工作に挑戦します。経験者には“常識”とされる内容も、本書では徹底的にわかりやすく解説。もう「何がわからないのかさえわからない」とは言わせません! さあ、本書であなただけの電子工作ライフを始めましょう!
こんな方にオススメ
- 電気・電子の基本を知りたい方
- 回路図を読めるようになりたい方
- 基礎的なパーツの役割を知っておきたい方
- ソフトウェアはわかるけどハードウェアが苦手だと感じる方
目次
第1章●電気の発見からトランジスタの発明まで
1-1 電気の発見から電池の発明
- 1-1-1 静電気と電気
- 1-1-2 電気の研究のはじまり
- 1-1-3 電池の発明と電気の発展
1-2 電気の研究ラッシュから電磁気学の完成
- 1-2-1 電磁気学の研究ラッシュ
- 1-2-2 電気の照明への活用
- 1-2-3 電気と磁気の関係に気づく
- 1-2-4 オームの法則の発見
- 1-2-5 電磁誘導現象の発見
- 1-2-6 電磁気学の完成と電磁波の予言
1-3 発電の歴史 ~ 直流から交流へ
- 1-3-1 直流発電機の発明による照明の発展
- 1-3-2 交流発電機の発明とエジソンの敗退
- 1-3-3 現在の交流送電システム
- 1-3-4 再び交流から直流へ
- 1-3-5 交流の特性
1-4 通信の歴史
- 1-4-1 通信の生い立ち
- 1-4-2 テレタイプ端末によるテレックスの発展
- 1-4-3 電話の発明
- 1-4-4 電波の存在の証明
- 1-4-5 無線通信のはじまり
1-5 電子の発見と電子の振る舞い
- 1-5-1 電子の発見と原子構造の解明
- 1-5-2 電気の源は自由電子
- 1-5-3 電子と静電気
- 1-5-4 電流を流す力 ~ 電圧
- コラム 電気の単位
1-6 ダイオードからトランジスタへ
- 1-6-1 n型半導体とp型半導体
- 1-6-2 接合型トランジスタの発明
- 1-6-3 電界効果トランジスタの発明
1-7 電子計算機からマイクロプロセッサの発明
- 1-7-1 電子計算機のはじまり
- 1-7-2 電卓戦争からマイクロプロセッサの発明へ
- 1-7-3 マイクロプロセッサの発展
1-8 モデム通信からインターネットへ
- 1-8-1 電話の発明からモデム通信が始まる
- 1-8-2 パケット通信からインターネットへ
第2章●電子工作の始め方
2-1 電子工作とは
- 2-1-1 電子工作の誕生
- 2-1-2 半導体素子とは
- 2-1-3 標準回路を活用する
2-2 電子工作を始めるには
- 2-2-1 対象物の動かし方を知る
- 2-2-2 動かすために必要なものを探す
- 2-2-3 電子回路を設計し、組み立てる
- 2-2-4 電子工作でできないこと
- 2-2-5 マイコンにより世界が広がる
2-3 電子工作に必要な道具
- 2-3-1 必須の道具
- 2-3-2 ケース加工用の道具
- コラム はんだ付けのコツ
2-4 電子工作にはパソコンが必須
2-5 電子工作の組み立て方法
- 2-5-1 ブレッドボードによる方法
- 2-5-2 ユニバーサル基板による方法
- 2-5-3 プリント基板を注文する方法
2-6 電子工作用の計測器の使い方
- 2-6-1 デジタルマルチメータ(DMM)
- 2-6-2 デジタルマルチメータの使い方
- 2-6-3 Analog Discovery3
- 2-6-4 オシロスコープとして使う
第3章●電子回路設計の基礎
3-1 回路図が読めて描けるようになるには
- 3-1-1 回路図の基本的な要素
- 3-1-2 回路には直流動作と交流動作がある
- 3-1-3 回路図に描いていないこと
- コラム グランドとは
3-2 抵抗の使い方
- 3-2-1 抵抗の使い方
- 3-2-2 抵抗は必ず発熱する
- 3-2-3 抵抗の種類
- 3-2-4 抵抗値
- 3-2-5 抵抗値とカラーコード
3-3 コンデンサの使い方
- 3-3-1 コンデンサの直流に対する特性
- 3-3-2 コンデンサの交流に対する特性
- 3-3-3 コンデンサの種類
- 3-3-4 容量値と定格電圧
3-4 コイルの使い方
- 3-4-1 コイルの直流に対する特性
- 3-4-2 コイルに交流を加えると
- 3-4-3 コイルの種類
3-5 能動部品の概要
- 3-5-1 能動部品とは
- 3-5-2 能動部品の選択ガイド
第4章●電源に何を使うか
4-1 電源の種類と使い方
- 4-1-1 電源の役割と種類
- 4-1-2 バッテリの種類と使い方
- 4-1-3 二次電池の充電方法
- 4-1-4 太陽電池の特性と使い方
- 4-1-5 ACアダプタの種類
- 4-1-6 AC/DC電源
4-2 太陽電池の使用例
- 4-2-1 ニッケル水素電池の充電器の全体構成
- 4-2-2 組み立て
4-3 実験用電源の製作
- 4-3-1 実験用電源の回路
- 4-3-2 アナログメータの使い方
- 4-3-3 組み立て
- 4-3-4 動作テストと調整
4-4 電源に関する不具合と対策
4-5 放熱の方法と放熱器
- 4-5-1 放熱の考え方
- 4-5-2 3端子レギュレータの放熱設計例
第5章●LEDを光らせたい
5-1 LEDの基本の使い方
- 5-1-1 LEDを光らせるには
- 5-1-2 フルカラーLEDの使い方
- 5-1-3 パワーLEDの使い方
5-2 明るさを可変するには
- 5-2-1 PWM制御とは
- 5-2-2 パワーLEDの調光制御器の製作
- 5-2-3 回路設計と組み立て
5-3 電池1個でLEDを光らせるには
- 5-3-1 LEDドライバとは
- 5-3-2 センサとの連動の製作
5-4 ソーラーライトの製作
- 5-4-1 全体構成
- 5-4-2 組み立て
- 5-4-3 動作確認
5-5 赤外線リモコン受信機の製作
- 5-5-1 全体構成
- 5-5-2 回路設計と組み立て
- 5-5-3 プログラムの製作
5-6 4桁の7セグLED時計の製作
- 5-6-1 全体構成
- 5-6-2 回路設計と組み立て
- 5-6-3 プログラムの製作
第6章●音を出したい
6-1 防犯ブザーの製作
- 6-1-1 全体構成
- 6-1-2 組み立て
- 6-1-3 動作確認
6-2 超簡単MP3プレーヤの製作
- 6-2-1 MP3プレーヤモジュールの外観と仕様
- 6-2-2 回路設計と組み立て
6-3 人検知メロディ再生器の製作
- 6-3-1 全体構成
- 6-3-2 回路設計
- 6-3-3 組み立て
6-4 感圧サウンド発生器の製作
- 6-4-1 回路図と組み立て
6-5 超音波距離計の製作
- 6-5-1 全体構成
- 6-5-2 回路設計と組み立て
- 6-5-3 プログラムの製作
第7章●ラジオを作りたい
7-1 FMモノラルラジオの製作
- 7-1-1 全体構成
7-2 スピーカの追加
- 7-2-1 スピーカを鳴らすには
- 7-2-2 回路設計と組み立て
7-3 マイコン制御のFMラジオ
- 7-3-1 全体構成
- 7-3-2 回路設計と組み立て
- 7-3-3 プログラムの製作
第8章●動くものを作りたい
8-1 RCサーボコントローラの製作
- 8-1-1 RCサーボとは
- 8-1-2 サーボコントローラの回路設計
- 8-1-3 サーボコントローラの製作
- 8-1-4 動作確認
8-2 ステッピングモータコントローラの製作
- 8-2-1 全体構成とモータ駆動方法
- 8-2-2 制御ボードの回路設計と組み立て
- 8-2-3 プログラムの製作
8-3 赤外線リモコンカーの製作
- 8-3-1 全体構成
- 8-3-2 車体の構成
- 8-3-3 回路設計と組み立て
- 8-3-4 プログラムの製作
第9章●センサデータを記録したい
9-1 PCにUSBシリアルで送信
- 9-1-1 IoT Board の製作
- 9-1-2 プログラムの製作
9-2 Wi-Fiでクラウドに送信
- 9-2-1 全体構成
- 9-2-2 プログラムの製作
付録
- 付録1 Raspberry Pi Pico Wの準備
- 付録2 表面実装ICのはんだ付け方法
- 付録3 Ambientの使い方