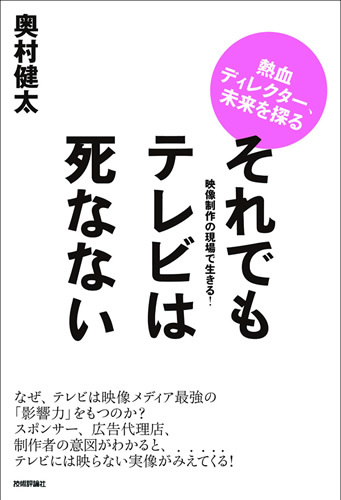今日は『それでもテレビは死なない――映像制作の現場で生きる!』(技術評論社刊)を上梓したばかりのテレビディレクター・奥村健太さんにお話を伺います。
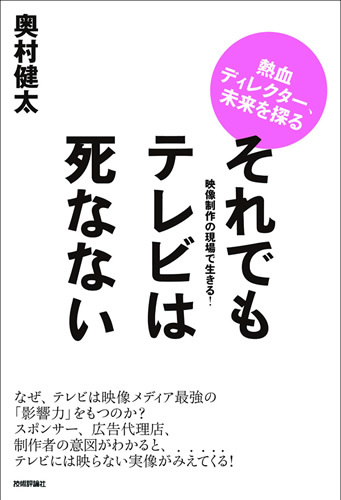
──タレントと懇意にしているようなテレビ局のプロデューサーや構成作家の名前はわりと知られていますが、基本的にテレビ制作者の名前は番組クレジットに出る程度で、表に出ることは多くはありませんよね。
そこで、テレビ番組制作に携わる奥村さんが、普段どんなお仕事をされているのかというところからうかがっていきたいと思います。簡単な自己紹介をお願いできますでしょうか。
報道番組やドキュメンタリー番組の企画を考えたり、取材をしたり、構成を考えたり、編集作業をしたり、ナレーション原稿を書いたり、お金(予算)の計算をしたり……番組制作全般に関わることです。あとは時間を見つけて、とにかくいろんな業界の人に会ってますね。情報交換というか、ネタ探しというか。趣味は特にないですが、料理は好きです。
本はジャンルを問わずたくさん読みますし、映画もよく観ますけど、あえて趣味とは言いません。読書をしない人もいないし、映画を観ない人もいないはずだから取り立てて挙げる必要はないのかな、とも思います。やっぱり何をしていても仕事の延長なので(笑)

──この何年かでテレビの現場で大きく変わったことはありますか。
一番大きな変化はやっぱり予算ですね。先立つものがないので、どんどん発想がショボく(笑)なっていっている印象です。でかい花火を打ち上げることをせずに、こじんまりと"それなり"の成果を上げようと考える人が増えているように感じます。あとはテロップなどのミスや視聴者からの指摘を異常に怖がるようになりました。上司に怒られたくない為だけに、無難な路線にすぐ舵を切ろうとする。
ちょっと話はズレるのですが、僕がまだペーペーのADだった頃に先輩に言われ続けた言葉があります。「番組は4つ立ち上げても、1つ成功すれば良いほうだ。何が受けるかなんて誰にもわからない。だからどんな番組でも全力でやり遂げろ。」
当時の僕には、番組の成功確率は25%か、打率低いなー、という印象以上に特に感想はなかったのですが、今ではこの言葉の意味がよく理解できます。全力で番組を立ち上げても25%の確率でしか成功しないのに、無難に番組を制作し続けようとしたら、面白いものが生まれる土壌そのものがなくなる、ということです。
リーマンショック以降、という表現でテレビの制作現場の衰退を指摘する声も多いのですが、ここ数年で失われたのは単に制作予算だけではなく、制作者自身の「覚悟」だというのが一番深刻な問題であると考えています。ちょっと格好つけすぎですかね(笑)
知ってほしいことはたくさんあるのに、放送時間に制限がある
──本書は、東日本大震災時の取材現場について多く触れられています。奥村さん自身は取材のなかで、どのような体験をされましたか。
飲まず食わず、という肉体的に困難な状況というより、テレビというメディアの力と凄さと弱さというものについて日々考えさせられるという、精神的に辛く厳しい状況が続きました。本の中でもいろいろと書きましたが、撮った素材が放送できないという辛さはかなりのものでしたね。テレビはずっと震災特番をやったとしても、1日と同じ長さ……24時間しか放送できません。
大量の映像素材の大半が視聴者の目に触れることなく素材保管庫に収められていく。被災者の方々も、どうせ撮っても放送しないんだろ、となるし、余震の恐怖に怯えながらの極限状況の中、取材対象である被災者の方々との信頼関係の構築が、これまでのどの現場よりも大変でした。
また、福島第一原発の事故関連の報道では、視聴者の方々との信頼関係が、一時期、完全に無くなったと感じていました。今まで当たり前だと思ってやってきていましたが、テレビ局というものがスポンサー──今回は東京電力ですが──にいかに頭が上がらないかということも身にしみて理解できました。話し始めると長くなるので、詳しくは本書を読んで頂ければ。

──テレビはヤラセやウソをついているのではないか、よくないウワサを聞きます。これは視聴者側からの単なる憶測なのでしょうか。
この問題を考える上で、一番重要なのは「ヤラセ」と「演出」の違いを知るということです。この本でもさまざまな事象を交えながら書きましたが、撮った映像素材をそのまま放送することは100%ありえないのがテレビです。取材者が体験して、カメラに収録された時間と空間を省略するために編集という作業が存在し、そのために視聴者はコンパクトにまとまった"良質な"情報を手軽に享受することができるのです。
現在のテレビの制作状況を鑑みると、この"良質な"というところに若干の疑問符がつくのですが、最も大きな問題は、視聴率を取るためにとか、ロケ時間がないからといった理由で、ありもしない出来事を本当に起きたことのように収録し放送することであり、これは「ヤラセ」として糾弾されて然るべきです。
もちろん、「ヤラセ」はない! と同じ業界の人間として断言したい所ではありますが、おそらく誰も気付いていない(発覚していない)だけで、ゼロと言い切ることはできないと思います。一方で実際に起きた事実を、編集という作業によって順番を入れ替えたり、エピソードを補足したりといった演出は、すべての番組において行われています。
この演出を指して、「ヤラセ」だ、と声高に叫ぶ向きがあるのは、ちょっと残念な気がしています。もっとテレビ番組制作の実際について知って欲しいな、と思いますし……。ただし、この演出のさじ加減がわかっていない制作者が多いのも事実なので、業界全体の能力値が下がっているということも、視聴者の憶測を生む要因のひとつなのかもしれません。残念なことですが。
マスに向けたテレビだから通る企画、やりにくい企画
──業界の暗い話題になってきてしまいました! これはこれで尽きないですけど、少し話を変えて、実際の番組制作についてうかがいますね。
奥村さんは、本書でも撮影協力いただいた「ラーメン二郎」にせっせと通い、番組を作ってしまうほどのジロリアンなんですよね。
たとえば、最近よく流れているだれもが知るファミレスやメーカーの人気ランキングを見るより、二郎の企画をもっと! というようなファンも多いと思うのですが、通向けの番組はなかなか通らないものなのでしょうか。
ラーメン二郎! くると思った、この質問(笑)。Ramen of Ramensである二郎は……(※編集部注:以下、ラーメン二郎関連話が20分以上も続いたのでここでは省略)。
どん! これがコアなファンからの絶大な支持を受ける1品(撮影協力・ラーメン二郎 ひばりヶ丘店)

冗談はさておき、テレビで有名ファミレスチェーンのランキングなどが紹介されることが多いのは、テレビがマス、つまり多数に向けて発信されるメディアだからということに他ならないんです。
日本全国津々浦々まで放送される全国ネットの番組、ま、一部地域を除くってこともありますが……では、番組を見る人が"その店を知っている"、または"その店に行ってみたくなる"ということが最低限の条件です。いわゆる視聴動機とも言えますが、その番組を見ることで、ちょっと得をするとか、知らなかったことを知ることができる。つまり番組を見続ける動機を視聴者に与え続けなくてはならないのです。
──なるほど。ニッチ、マス……企画ごとに読者対象を考える書籍出版とは最初に向ける母数がちがいますよね。
本の中でも散々言及していますが、賛否両論あるにせよ、テレビにとって視聴率というものは絶対的な物差しです。毎00秒ごとに訪れるカウントチャンスを毎分どうやって乗り切っていくか、制作者たちは常に頭を悩ませています。そんな熾烈な戦いが繰り広げられている中、ラーメン二郎がどれだけ有名だとは言え、いわゆる直系の店舗が都内を中心に30数店しかない以上、やはり数百店舗を数えるチェーン店には知名度では遥かに及びません。関東地方でしか放送しない深夜番組ならいざしらず、ゴールデンタイムの全国ネットの番組ともなると、どちらが「視聴率」を取る企画書として優れているか、言うまでもありません。
ただ、僕はそういうマスに向けた番組にはあまり興味がないようで、マニアックな題材でなおかつ後にDVD化されるような良質な番組を作り続けたいと考えています。ラーメン二郎の若き店主たちとは個人的にも親しくさせてもらっていますが、彼らのドキュメンタリー番組なんて絶対に面白いと思うんですよね! 今、企画を考え中で……(※編集部注:以下、またしてもラーメン二郎関連の話が延々と続いたので省略)。
──ラーメン二郎のドキュメンタリー番組、ぜひ見たいです。
さて、奥村さんは、さまざまな現場を経験されていますが、どのジャンルの制作が一番楽しいというのはありますか?
殺人事件の現場リポートから、カルト教団の潜入取材、雪山に登って遭難しかかったり、大ヒット少女漫画の秘密を探ったりと、硬軟併せてありとあらゆる現場の取材をしていますが、やっぱり一番やっていて楽しくて好きなのは、秘境系のドキュメンタリー番組です。
誰も行ったことのない場所で、誰も撮影したことのない事象や人物にカメラを向ける。参考にするテキストもなければ、先人の本もない。自分と取材対象とのまさに真剣勝負です。この首筋がヒリヒリするような感覚は他ではちょっと味わえません。視聴者に、これまでに見たことのないような映像を届けるという意味では、こんなにワクワクする仕事はないんじゃないでしょうか。

もちろんそこに辿り着くまでに死にそうな目に遭ったりもしますし、取材者なんだか、冒険者なんだかよくわからなくなっている状況も多々あるのですけど。
そのあたりのエピソードは本書のコラムにいろいろと書いたので、是非、読んでみてください。でも、こういったドキュメンタリー番組は、予算がかかる割に視聴率が取れないので、最近のテレビ、特に地上波では敬遠されがちです。なんとかしたいと常に考えているのですが……。
──最後に『テレビは死なない』と挑戦的なタイトルに加え、「こんなこと言って大丈夫?」というネタまで、真面目に鋭く書いていただいた本書ですが、読者のみなさまにひと言お願いします。
今回の本は、いわゆる「暴露本」ではありません。匿名で、面白可笑しく無責任にテレビ業界の内幕を書きまくる、という選択肢は最初からありませんでした。同じ業界で働く人たちはもちろん、「テレビなんてヤラセばっかり!」と思っている方々にも、制作の現場がどうなっているのか知ってほしいと思いますし、これからテレビ業界を目指す学生さんには是非読んでもらいたいです。
センセーショナルかどうかと言われれば、それは読者の皆さんの受け止め方次第ですが、"現場の人間でしかわからないこと"という意味では、かなり濃い中身だと思います。ということで、今までありそうでなかった1冊になった、という自負はあります。まぁ、誰かに怒られるかもしれませんが、それはそれでズバリ、的を得ていたということで(笑)。
──本日は、お忙しいなかありがとうございました。
テレビマンの舞台裏から番組作りのひみつまで、現場の視点で描かれた『それでもテレビは死なない』好評発売中です。是非、お手にとってください。
「序章」試し読みができますので、こちらからどうぞ